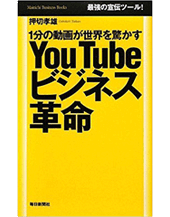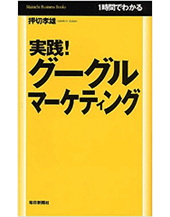査読付き論文の書き方

こんにちは、押切孝雄です。
研究者にとって重要なことがいくつかありますが、
その1つは論文を書くことです。
論文には2通りあり、査読付きの論文と査読なしの論文があります。
その違いや査読付き論文の書き方とはどのようなものでしょうか?
個人的に、この1年間は論文に向き合った1年間でした。
今年度は、論文を3本書きました。
2本は単著(査読なし)です。
1本は査読付き論文で共著です。
論文(査読なし)
査読のつかない論文は自分で思うように書いていきます。
自分でこれなら研究者として恥ずかしくないと書ききったところで提出となります。
査読のない論文については、リジェクトされることなく提出となります。
それに対して査読付き論文は論文を審査に出してからがポイントです。
査読つき論文
査読付き論文は、複数名の査読者からの審査をうけるということです。
学会誌に掲載されることになりますので、
査読者が複数人(おおよそ3人くらい)ついて査読されます。
ちなみに査読は通常「ブラインド」で行われますので、
論文を書く人も査読者もお互いのことを知りません。
論文を書く人は名前を伏せて書きます。
また論文を書いた人も誰が査読者なのか分かりません。
このようにして論文が査読されます。
そして、その論文が詳細に読まれ、さまざまなポイントを指摘されます。
論文はリジェクトされることもある
査読に出してすんなり通ると言う事は稀で、
多くの場合、指摘されて戻ってきます。
共著で書いた私の経験でも、多くのポイントを指摘されました。
しかし、その指摘はリジェクトでなければ、ポジティブに捉えるべきです。
実際に、査読結果の内容を見ると、
「こういう切り口があったのか!」
と論文執筆者自身が気づかなかったような点を指摘いただけることが多々あります。
(まさに、今回がそれでした)
そして、執筆陣は、その指摘されたポイントについて一つ一つ対応していくことになります。
今回共著でしたので3人で分担して書いていきました。
論文の内容に対する指摘だけでなく、
今回は英語で書いた論文だったため、英語の語法に関するポイントも指摘されました。
詳細に指摘いただいたため、
査読の先生方は、我々の論文をここまでしっかり読み込んでくれていて、
本当にしっかり見てくれてるというのが率直な感想です。
学会誌(査読誌)に載る意味
査読を受けるという事は
ジャーナル誌に載るレベルまで論文の完成度を高めるということです。
実際には、その前のプロセスで査読結果が戻ってくると直しが多いので心理的にはきついです。
ただ、リジェクトされたわけではありません。
誠実に向き合って、直していけばいいのです。
1人だったらうちのめされていたと思いますが、
今回の論文は3人の共著だったため、
他の2人が、経験の豊富な先生方でありましたし、
1つ1つ丁寧さを心がけて修正し、鼓舞しあって乗り切ることができました。
査読付き論文で大変な思いをされている研究者の人も少なくないと思います。
ただ、それを乗り越えることは、少なからず良い経験となります。
そんな査読付き論文を、先日、ちょうど再提出し終えたところです。
社会的に意義のある研究を1つ1つ進めていきたいと思います。